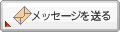2011年07月23日
なんでもや(大張物産センター)
沖縄の共同売店をモデルに、過疎に悩む地域の住民同士が出資して設立、運営しているお店が全国各地に出てきています。
その代表ともいえるのが、宮城県の丸森町大張地区にある「大張物産センター なんでもや」さんです。
このブログではもちろん、ことあるごとに紹介しているので(最初はこちらの記事でした)、ご存知の方はご存知のはずですが、youtubeに総務省地域づくり表彰のビデオがアップされていたので紹介しますね。
奥共同店との交流は今も続いています。
奥からは新茶を送り、なんでもやさんからはお米が届きます。またお互いの記念行事には行き来しておられます。
また東北の大震災後、奥の皆さんがこんな声援も送っておられました!なんでもやさんのブログ「なんでもやに来てね!」のこちらとこちら。
沖縄の共同店というモデルがあったとはいえ、やはり真似すれば誰にでもできる訳ではない、という気がしました。
強い危機感を大張の皆さんが共有していて、しかも使命感から率先して動いたキーパーソンがいて、それを皆で支え、さまざまに努力されていることがビデオからよく分かりました。
同じようなケースで思い出すのは、広島県安芸高田市、川根振興協議会が運営している「万屋」さん。こちらでは辻駒健二さんという方が地域を引っ張っておられました。
こちらもいつか紹介したいと思っています。
でも山形県の役場の方がおっしゃっていたように、「自分のところのことは自分たちでやるという思いがあれば、やればできるんだな」というのも、きっと事実なんだと思います。
やればできる、やらなきゃできない、、、。
その代表ともいえるのが、宮城県の丸森町大張地区にある「大張物産センター なんでもや」さんです。
このブログではもちろん、ことあるごとに紹介しているので(最初はこちらの記事でした)、ご存知の方はご存知のはずですが、youtubeに総務省地域づくり表彰のビデオがアップされていたので紹介しますね。
奥共同店との交流は今も続いています。
奥からは新茶を送り、なんでもやさんからはお米が届きます。またお互いの記念行事には行き来しておられます。
また東北の大震災後、奥の皆さんがこんな声援も送っておられました!なんでもやさんのブログ「なんでもやに来てね!」のこちらとこちら。
沖縄の共同店というモデルがあったとはいえ、やはり真似すれば誰にでもできる訳ではない、という気がしました。
強い危機感を大張の皆さんが共有していて、しかも使命感から率先して動いたキーパーソンがいて、それを皆で支え、さまざまに努力されていることがビデオからよく分かりました。
同じようなケースで思い出すのは、広島県安芸高田市、川根振興協議会が運営している「万屋」さん。こちらでは辻駒健二さんという方が地域を引っ張っておられました。
こちらもいつか紹介したいと思っています。
でも山形県の役場の方がおっしゃっていたように、「自分のところのことは自分たちでやるという思いがあれば、やればできるんだな」というのも、きっと事実なんだと思います。
やればできる、やらなきゃできない、、、。
<財団法人地域活性化センター 平成19年度地域つくり総務大臣表彰>
一見、普通の食料品や雑貨を扱う店舗に見えるこのお店。
実は、地域の暮らしを守るため、住民が共同で始めた地域の宝ともいうべきお店なのです。
そのお店の名前は、なんでもや。
<地域を守るみんなのお店 大張物産センター なんでもや>
宮城県伊具郡丸森町。宮城県の最南端に位置し、福島県と隣接しています。
町の北部を流れる阿武隈川。江戸時代には年貢米が、明治時代には町で採れる材木、木炭、石材が船を使って運ばれていました。
役場のある町の中心から西へおよそ10キロ進んだところにある集落、大張地区。310世帯が暮らしています。
地区内にある沢尻の棚田は、日本棚田百選にも選ばれています。
そんな大張地区に、大張物産センターなんでもやはあります。
なんでもやの誕生は平成15年。大張地区に唯一残っていた小売店の閉店がきっかけでした。
買い物をしようにも隣接する角田市や白石市までは車で20分近くかかります。
<大張物産センターなんでもや 代表・中村次男さん>
「地元のほれ、高齢者の人が買うとこがなくなっちゃったんでね、ちょっとした買い物でも、ほれ、全部町に行くような方になっちゃって。とにかく不便だから何とか地域に店があればいいんだなって話になったんですね」
そんな時、沖縄で営まれて共同店を開いてはどうか、という提案が持ち上がりました。
共同店とは、明治39年に沖縄県で始まった、地域の人々が共同で出資して作った売店のことです。
<沖縄・奥共同店>
島の暮らしの支えてきたこのシステムを、大張地区でも実践できないかというのです。
地域の人々で作るお店、その実現に向けて中村さんたち有志は動きだしました。
大張地区の世帯にそれぞれ二千円の出資を呼びかけ、310世帯のうち200世帯から賛同を得ました。
その他、商工会員からそれぞれ10万円ずつ出資してもらうなど、合計で200万円の出資金が集まりました。
こうして平成15年12月、大張物産センターが開店。場所はかつてJA大張支所の購買部があった店舗を格安で借りることができました。
地域に暮らす人が必要とするものは、なんでも取り扱おうという思いから、店の名前は「なんでもや」と名付けられました。
<大張物産センターなんでもや 店長 佐久間憲治さん>
「住民の皆さんのご協力によって、棚は大工さんたちが奉仕でやってもらいまして、あと冷蔵庫もいろいろな都合上で、ほとんどタダ同様に協力頂いた、いうような形で始まった。一年でだいたい一千万も売れればいいかなというような感じでいたんですが、おかげさまで皆様のご協力によって、3200万ほど売り上げまして、2年目は3600万ほど、そして3年目は4000万を突破した」
開店から5年、住民自ら地域を守っていこうという姿勢が高く評価され、大張物産センターなんでもやは、平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。
では、なんでもやの地域に根ざした取り組みとはどのようなものなのでしょうか。
13坪の店内には、大張地区をはじめとする丸森町内の農家が委託している野菜が販売されています。
この日も地域の人が自分の畑で作った野菜を持ってきました。
自分で食べるためだけのために作っていた野菜を売る場所ができた、そして買った人の反応が直にわかる。
このことが畑を持つ高齢者のみ大きな励みになっています。
野菜の他にも、なんでもやでは、名前の通りなんでも売っています。日用雑貨、食料品、何と自動車まで販売しています。中にはこんなものまで。<まむし焼き>
買い物に立ち寄るだけではなく、住民同士のコミュニケーションの場としても機能しているのです。
「非常に便利ですし、うちは助かってますね」
「新鮮だしね、安いしね」
「大張地区としては、一番頼りにしている」
オープンから2年目には、店舗の隣に調理場を新設しました。
一人暮らしの高齢者にとって、魚の調理や揚げ物は危険です。1人分の食事を作るのも、決して楽ではありません。
その苦労を少しでも減らし、楽しく食事をしてもらいたいという願いから建てられました。
<佐久間店長>
「てんぷらを揚げるといっても高齢者には危険だと。天ぷら食べたくても食べられないと。高齢者の皆さん、油使うのも嫌だと、いうような感じなものですから、こちらで全部、加工して持っていくと、それが一番の人気ですね」
かつて飲食店を経営していた佐久間さん。慣れた手つきで魚をさばいていきます。
調理の合間を縫って佐久間さんは、お隣の角田市に向かいます。
「こんにちは」
調理場では作りきれない、揚げ物や焼き魚を、飲食店時代に付き合いのあった肉屋さんや魚屋さんにお願いしているのです。
お肉屋さん自慢の揚げ物は大好評。地域の人の喜ぶ顔があるからこそ佐久間さんは頑張るのです。
「今度はね、豆腐を取りに」
販売を終えて佐久間さんが向かったのは、佐藤す江さんの営む豆腐屋さんです。
<佐藤豆腐店>
す江さんは40年間、家族で豆腐屋を経営してきました。一人暮らしになってからは豆腐作りを休んでいましたが、なんでもや開店に伴って再び始めました。
地域の高齢者が、なんでもやによって活力を取り戻したのです。
<佐藤豆腐店 佐藤す江さん>
「作りががいがあるね。毎日ほれ、なんでもやさんが来てもらってね、持っていかれるからね」
昔ながらの手作りの豆腐は、1日限定24丁。大豆の濃厚な味が評判になり、毎日売り切れます。
この日は大張地区の児童館から、お弁当の注文がありました。
<丸森町 大張児童館>
「はい、ありがとうござます」「わあ、おいしそう」「いただきます!」
地域の施設においしい食事を届けるのも、なんでもやの担う大切な仕事のひとつなのです。
今度は保冷車にお豆腐や焼き魚を積み込んで、移動販売に向かいます。佐久間さん大忙しです。
店舗に来るのも難しい、車を運転できない高齢者のために、佐久間さん自ら一軒一軒尋ねていって、売り歩くのです。
廻るお宅はおそよ30軒。毎週木曜日の移動販売を、みんな楽しみにしています。
お土産を持たせてくれるおばあちゃんも。
移動販売は単なる売り買いだけではなく、一人暮らしの高齢者の健康の確認などの役目も果たしています。
「いつでも買えないから待ってるんだわ」
「やっぱり便利だね、ええ」
「これで満足、少し楽ちんするから」
佐久間さんとお客さんとの会話の風景。行く先で笑い声が絶えません。
日曜日。お隣の山形県にある、西川町大井沢地区から視察団がやってきました。
共同店という、東北ではまだ珍しい試みをぜひ参考にしたいと尋ねてきたのです。
佐久間さん自ら、なんでもやの取り組みについて説明します。
熱心に耳を傾ける視察の人々。
<山形県西川町役場 産業振興課 農林係長 志田龍太郎さん>
「ウチの町でも、まあ地区ですけど、今年店がなくなりまして、そんなことでなんか、こういった情報を前から聞いていたものですから、ぜひこういった同じような店をですね、やってみたいという。やればできるんだ、というところをねすね、一番印象深くて、感心したところですけども。あとはやっぱりその、自分たちのところは自分たちで取り組むんだという、そういったその地域性が丸森町全体、それからここの大張地区にもあるのかなと」
他県からは年間およそ30件の視察団が訪れます。
まもなく5周年を迎えるなんでもや。
しばらく休刊していた広報誌「なんでもや新聞」を再び発行しようという動きが出てきました。
作っているのは常連のお母さんたち。
「子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで皆一緒に、なにかしら楽しくやるきっかけになっているのが、このなんでもやかなというふうに感じています。だからちょっとでも手伝える、何か協力できるものがあればと。楽しみながら完成させよう、っていうところですね」
店長の佐久間さんや代表の中村さんも、今後のなんでもやの展望を考えています。
「これからやっぱり、ますます高齢者が多くなってくるということで、夜の惣菜を何とか1食200円足らずで宅配できれば、高齢者の皆さんにもいいんではないかなと思って、そういったことも今後考えていきたいなと思っております」
「地域が、極端な言い方だと、大きな家族みたいな形じゃないですかね。地域の人はみんな知ってるし、高齢化が進んでますけど、やっぱり地域の皆さんが仲良くいつまでも一緒にやっていきたいなと」
大張の暮らしを支えるみんなのお店。
なんでもやには今日も笑顔が溢れています。
<企画・財団法人地域活性化センター、制作・NPOネットジャーナリスト協会>
一見、普通の食料品や雑貨を扱う店舗に見えるこのお店。
実は、地域の暮らしを守るため、住民が共同で始めた地域の宝ともいうべきお店なのです。
そのお店の名前は、なんでもや。
<地域を守るみんなのお店 大張物産センター なんでもや>
宮城県伊具郡丸森町。宮城県の最南端に位置し、福島県と隣接しています。
町の北部を流れる阿武隈川。江戸時代には年貢米が、明治時代には町で採れる材木、木炭、石材が船を使って運ばれていました。
役場のある町の中心から西へおよそ10キロ進んだところにある集落、大張地区。310世帯が暮らしています。
地区内にある沢尻の棚田は、日本棚田百選にも選ばれています。
そんな大張地区に、大張物産センターなんでもやはあります。
なんでもやの誕生は平成15年。大張地区に唯一残っていた小売店の閉店がきっかけでした。
買い物をしようにも隣接する角田市や白石市までは車で20分近くかかります。
<大張物産センターなんでもや 代表・中村次男さん>
「地元のほれ、高齢者の人が買うとこがなくなっちゃったんでね、ちょっとした買い物でも、ほれ、全部町に行くような方になっちゃって。とにかく不便だから何とか地域に店があればいいんだなって話になったんですね」
そんな時、沖縄で営まれて共同店を開いてはどうか、という提案が持ち上がりました。
共同店とは、明治39年に沖縄県で始まった、地域の人々が共同で出資して作った売店のことです。
<沖縄・奥共同店>
島の暮らしの支えてきたこのシステムを、大張地区でも実践できないかというのです。
地域の人々で作るお店、その実現に向けて中村さんたち有志は動きだしました。
大張地区の世帯にそれぞれ二千円の出資を呼びかけ、310世帯のうち200世帯から賛同を得ました。
その他、商工会員からそれぞれ10万円ずつ出資してもらうなど、合計で200万円の出資金が集まりました。
こうして平成15年12月、大張物産センターが開店。場所はかつてJA大張支所の購買部があった店舗を格安で借りることができました。
地域に暮らす人が必要とするものは、なんでも取り扱おうという思いから、店の名前は「なんでもや」と名付けられました。
<大張物産センターなんでもや 店長 佐久間憲治さん>
「住民の皆さんのご協力によって、棚は大工さんたちが奉仕でやってもらいまして、あと冷蔵庫もいろいろな都合上で、ほとんどタダ同様に協力頂いた、いうような形で始まった。一年でだいたい一千万も売れればいいかなというような感じでいたんですが、おかげさまで皆様のご協力によって、3200万ほど売り上げまして、2年目は3600万ほど、そして3年目は4000万を突破した」
開店から5年、住民自ら地域を守っていこうという姿勢が高く評価され、大張物産センターなんでもやは、平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。
では、なんでもやの地域に根ざした取り組みとはどのようなものなのでしょうか。
13坪の店内には、大張地区をはじめとする丸森町内の農家が委託している野菜が販売されています。
この日も地域の人が自分の畑で作った野菜を持ってきました。
自分で食べるためだけのために作っていた野菜を売る場所ができた、そして買った人の反応が直にわかる。
このことが畑を持つ高齢者のみ大きな励みになっています。
野菜の他にも、なんでもやでは、名前の通りなんでも売っています。日用雑貨、食料品、何と自動車まで販売しています。中にはこんなものまで。<まむし焼き>
買い物に立ち寄るだけではなく、住民同士のコミュニケーションの場としても機能しているのです。
「非常に便利ですし、うちは助かってますね」
「新鮮だしね、安いしね」
「大張地区としては、一番頼りにしている」
オープンから2年目には、店舗の隣に調理場を新設しました。
一人暮らしの高齢者にとって、魚の調理や揚げ物は危険です。1人分の食事を作るのも、決して楽ではありません。
その苦労を少しでも減らし、楽しく食事をしてもらいたいという願いから建てられました。
<佐久間店長>
「てんぷらを揚げるといっても高齢者には危険だと。天ぷら食べたくても食べられないと。高齢者の皆さん、油使うのも嫌だと、いうような感じなものですから、こちらで全部、加工して持っていくと、それが一番の人気ですね」
かつて飲食店を経営していた佐久間さん。慣れた手つきで魚をさばいていきます。
調理の合間を縫って佐久間さんは、お隣の角田市に向かいます。
「こんにちは」
調理場では作りきれない、揚げ物や焼き魚を、飲食店時代に付き合いのあった肉屋さんや魚屋さんにお願いしているのです。
お肉屋さん自慢の揚げ物は大好評。地域の人の喜ぶ顔があるからこそ佐久間さんは頑張るのです。
「今度はね、豆腐を取りに」
販売を終えて佐久間さんが向かったのは、佐藤す江さんの営む豆腐屋さんです。
<佐藤豆腐店>
す江さんは40年間、家族で豆腐屋を経営してきました。一人暮らしになってからは豆腐作りを休んでいましたが、なんでもや開店に伴って再び始めました。
地域の高齢者が、なんでもやによって活力を取り戻したのです。
<佐藤豆腐店 佐藤す江さん>
「作りががいがあるね。毎日ほれ、なんでもやさんが来てもらってね、持っていかれるからね」
昔ながらの手作りの豆腐は、1日限定24丁。大豆の濃厚な味が評判になり、毎日売り切れます。
この日は大張地区の児童館から、お弁当の注文がありました。
<丸森町 大張児童館>
「はい、ありがとうござます」「わあ、おいしそう」「いただきます!」
地域の施設においしい食事を届けるのも、なんでもやの担う大切な仕事のひとつなのです。
今度は保冷車にお豆腐や焼き魚を積み込んで、移動販売に向かいます。佐久間さん大忙しです。
店舗に来るのも難しい、車を運転できない高齢者のために、佐久間さん自ら一軒一軒尋ねていって、売り歩くのです。
廻るお宅はおそよ30軒。毎週木曜日の移動販売を、みんな楽しみにしています。
お土産を持たせてくれるおばあちゃんも。
移動販売は単なる売り買いだけではなく、一人暮らしの高齢者の健康の確認などの役目も果たしています。
「いつでも買えないから待ってるんだわ」
「やっぱり便利だね、ええ」
「これで満足、少し楽ちんするから」
佐久間さんとお客さんとの会話の風景。行く先で笑い声が絶えません。
日曜日。お隣の山形県にある、西川町大井沢地区から視察団がやってきました。
共同店という、東北ではまだ珍しい試みをぜひ参考にしたいと尋ねてきたのです。
佐久間さん自ら、なんでもやの取り組みについて説明します。
熱心に耳を傾ける視察の人々。
<山形県西川町役場 産業振興課 農林係長 志田龍太郎さん>
「ウチの町でも、まあ地区ですけど、今年店がなくなりまして、そんなことでなんか、こういった情報を前から聞いていたものですから、ぜひこういった同じような店をですね、やってみたいという。やればできるんだ、というところをねすね、一番印象深くて、感心したところですけども。あとはやっぱりその、自分たちのところは自分たちで取り組むんだという、そういったその地域性が丸森町全体、それからここの大張地区にもあるのかなと」
他県からは年間およそ30件の視察団が訪れます。
まもなく5周年を迎えるなんでもや。
しばらく休刊していた広報誌「なんでもや新聞」を再び発行しようという動きが出てきました。
作っているのは常連のお母さんたち。
「子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで皆一緒に、なにかしら楽しくやるきっかけになっているのが、このなんでもやかなというふうに感じています。だからちょっとでも手伝える、何か協力できるものがあればと。楽しみながら完成させよう、っていうところですね」
店長の佐久間さんや代表の中村さんも、今後のなんでもやの展望を考えています。
「これからやっぱり、ますます高齢者が多くなってくるということで、夜の惣菜を何とか1食200円足らずで宅配できれば、高齢者の皆さんにもいいんではないかなと思って、そういったことも今後考えていきたいなと思っております」
「地域が、極端な言い方だと、大きな家族みたいな形じゃないですかね。地域の人はみんな知ってるし、高齢化が進んでますけど、やっぱり地域の皆さんが仲良くいつまでも一緒にやっていきたいなと」
大張の暮らしを支えるみんなのお店。
なんでもやには今日も笑顔が溢れています。
<企画・財団法人地域活性化センター、制作・NPOネットジャーナリスト協会>
Posted by mkat at 22:09│Comments(3)
│全国に広がる住民出資の店
この記事へのコメント
宮城県丸森町大張物産センターなんでもやです。
100周年祭の際には大変お世話になりました。また、この度の大震災時には、沖縄の皆さんからの心温まるメッセージ、そして力づけられる鯉のぼり、本当にありがとうございました。当店がある丸森町は震災の被害は少なく、今はもとの生活が送れるようになりました。ただ、放射能の問題や余震が続き、何かに怯えながらの生活といった面も見られます。そんな状況ではありますが、なんでもやスタッフ一同、また、私たちの支えとなる地域住民のみなさんは毎日元気に過ごしております。この秋には恒例となりましたなんでもや創業祭も開催予定です。機会がございましたら、眞喜志さんもぜひおいでください!
100周年祭の際には大変お世話になりました。また、この度の大震災時には、沖縄の皆さんからの心温まるメッセージ、そして力づけられる鯉のぼり、本当にありがとうございました。当店がある丸森町は震災の被害は少なく、今はもとの生活が送れるようになりました。ただ、放射能の問題や余震が続き、何かに怯えながらの生活といった面も見られます。そんな状況ではありますが、なんでもやスタッフ一同、また、私たちの支えとなる地域住民のみなさんは毎日元気に過ごしております。この秋には恒例となりましたなんでもや創業祭も開催予定です。機会がございましたら、眞喜志さんもぜひおいでください!
Posted by 大張物産センターなんでもや at 2011年08月17日 13:16
なんでもやさん、コメントありがとうございます!
皆さんの頑張りに沖縄の人たちの方が勇気づけられています。
逆に喝を入れてもらわなきゃいけないですかね~。
創業祭、いつかぜひ行こうと思っています!
ブログも楽しみにしていますよ~
皆さんの頑張りに沖縄の人たちの方が勇気づけられています。
逆に喝を入れてもらわなきゃいけないですかね~。
創業祭、いつかぜひ行こうと思っています!
ブログも楽しみにしていますよ~
Posted by マキシ at 2011年08月20日 18:07
at 2011年08月20日 18:07
 at 2011年08月20日 18:07
at 2011年08月20日 18:07ご感想は、ブログ左コラムの「お問合せはコチラから」より、メッセージをお送り下さい!
Posted by マキシ at 2015年06月07日 23:41
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。